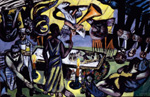展覧会概要
「日本におけるドイツ年」の最後を飾る大規模展「東京−ベルリン/ベルリン−東京展」は、日本とドイツそれぞれの首都である2つの都市間で、19世紀末から繰り広げられてきた文化・芸術的交流の軌跡をたどる展覧会です。二度の大戦、大地震、高度経済成長、イデオロギーの崩壊、不況など、両都市ともに崩壊と再興を繰り返してきた20世紀、美術の歴史に限らず、建築、写真、デザイン、演劇など幅広いジャンルで多くの興味深い交流や接点がありました。展覧会もその歴史を追いながら11のセクションに分け、約500点をご紹介します。
前半は、現存するネオ・バロック様式の司法省(法務省旧本館、1888年着工)を設計したベルリンの建築家エンデ&ベックマン、作曲家・山田耕筰などがベルリンから持ち帰った「シュトゥルム画廊木版画展」(1914年)、ベルリンでロシア・アヴァンギャルドやイタリアの未来派、ベルリン・ダダなど当時の欧州で最も前衛的な芸術運動を吸収し、帰国後に「マヴォ」旋風(1923年)を巻き起こした村山知義、新興写真家に多大な影響を与えた「独逸国際移動写真展」(1931年)など、当時の東京の芸術界を大きく動かした一展覧会や個人に注目してみることができるでしょう。また、1933年にベルリンで閉校した総合造形学校「バウハウス」では、山脇 巖、水谷武彦などが学び、その後ナチス台頭のドイツから逃れてブルーノ・タウトが来日するなど、日本の建築やデザイン分野と同校の関係も探ります。
後半は、両都市が第二次大戦へ向かった1930年代後半、さらには敗戦と都市の崩壊から新しく起ち上がった1945年から50年代の、社会全体の動きと芸術活動の関係性を追うことができます。さらに、ニューヨークを中心とした「フルクサス」が東京とベルリンを繋ぐなど、前衛芸術運動がパラレルに花開いた1960年代も興味深いところです。そして、展覧会の最後には、1989年の壁崩壊以降、首都へ返り咲いたベルリンで、新旧の歴史が共存する都市から活発に創出されるコンテンポラリー・アートの数々をダイナミックにご紹介します。
「東京−ベルリン/ベルリン−東京展」は、2006年6月にベルリンの国立新美術館に巡回します。

東京−ベルリン展ポスター 国際広告賞で金賞を受賞!
11の展示セクション
- ベルリン−東京 1880-1914 異国趣味と近代の意識
- 「シュトゥルム木版画展」 東京 1914年 前衛の衝撃
- 東京−ベルリン 1912-1923 美術と建築の新しいヴィジョン
- 衝突する文化 1918-1925 ベルリン・ダダ、東京の「マヴォ」とロシア革命の影響
- モガとモボ 1920年代のベルリンと東京のモダンガール、モダンボーイ
- 「独逸国際移動写真展」 1929-1931 写真の新たなアプローチ
- バウハウスとブルーノ・タウト 1930年代の建築とデザイン
- 暗黒の時代 1931-1945 独裁制、抵抗、戦争
- 復興の時代 1945-1950年代
- フルクサス、ポップアートと新表現主義 1960年代の前衛芸術
- ベルリンの今 壁崩壊後の現代美術
アーティスト

フランツ・アッカーマン
赤松麟作
赤瀬川原平
ヨーゼフ・アルバース
靉嘔
梅堂国政/(四代歌川国政)
ゲオルク・バゼリッツ
ヘルベルト・バイヤー
マックス・ベックマン
ヨーゼフ・ボイス
エンネ・ビーアマン
ヴィルヘルム・ベックマン
キャンディス・ブレイツ
マリアンネ・ブレスラウアー
マルセル・ブロイヤー
分離派建築会
マックス・ブルヒャルツ
ダヴィト・ブルリューク
ズーゼ・ビュク
シャルゲスハイマー
ローヴィス・コリント
土門 拳
瑛九
ヘルマン・エンデ
アニカ・エリクソン
ハンス・フィンスラー
アルノ・フィッシャー
ニナ・フィッシャー/マロアン・エル・ザニ
福沢一郎
普門 暁
ヴァルター・フンカート
古川成俊
古沢岩美
フレッド・グラーヴェンホルスト
ヴァルター・グロピウス
カタリーナ・グロッセ
ジョージ・グロス
ハンス・グルンディヒ
波々伯部金洲
アウグスト・ハイドゥク
ハインツ・ハイェク=ハルケ
浜松小源太
濱谷 浩
ハナヤ勘兵衛
長谷川 潔
ラウール・ハウスマン
林 忠彦
ジョン・ハートフィールド
エーリヒ・ヘッケル
フローランス・アンリ
樋口忠男
平井輝七
ハナ・ヘーヒ
カール・ホーファー
本庄光郎
堀野正雄
一曜斎国輝(二代歌川国輝)
池部 鈞
井上安治
石井茂雄
石本喜久治
岩宮武二
ユリウス・ヤーコプ
実験工房
影山光洋
神原 泰
ヴァシリー・カンディンスキー
勝川春亭
川端龍子
河辺昌久
川上涼花
河原 温
ペーター・キートマン
型而工房
木村伊兵衛
エルンスト・ルートヴィヒ・キルヒナー
岸田劉生
小林万吾
古賀春江
小石 清
オスカー・ココシュカ
ゲオルク・コルべ
ケーテ・コルヴィッツ
今 和次郎
小杉武久
工藤哲巳
草間彌生
桑原甲子雄
マルティン・リープシャー
ヴァシリー・ルックハルト
町田隆要
ジャンヌ・マメン
フランツ・マルク
エリ・マルクス
ルートヴィヒ・マイトナー
エーリヒ・メンデルゾーン
アドルフ・フォン・メンツェル
ハラルト・メツケス
ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエ
ボリス・ミハイロフ
三瀬幸一
水谷武彦
ラースロー・モホイ=ナジ
ヴィルヘルム・モルグナー
師岡宏次
村山知義
ヘルマン・ムテジウス
長野重一
永野芳光
中原 實
中村研一
中西夏之
中山岩太
難波香久三(架空像)
名取洋之助
エルンスト・ヴィルヘルム・ナイ
オスカー・ネルリンガー
エミール・ノルデ
岡本太郎
大久保好六
恩地孝四郎
エミール・オルリック
ナム・ジュン・パイク
ヴィクトル・パリモフ
マックス・ペヒシュタイン
ヴァルター・ペーターハンス
ハンス・ペルツィヒ
アルベルト・レンガー=パッチュ
ダニエル・リヒター
ヴェルナー・ローデ
ヴィリー・レーマー
ハヨ・ローゼ
シャルロッテ・ルドルフ
フリッツ・ルンプ
佐伯春虹
澤田哲郎
クリスティアン・シャート
カール・シュミット=ロットルフ
オイゲン・シェーネベック
クルト・シュヴィッタース
フリードリヒ・ザイデンシュテュッカー
塩見允枝子
白瀧幾之助
オットー・シュタイナート
ヤーコプ・シュタインハルト
グンタ・シュテルツル
サーシャ・ストーン
ホルスト・シュトレンペル
杉浦非水
住谷磐根
高松次郎
滝沢真弓
玉村方久斗(善之助)
ゲオルク・タッペルト
タイガー立石
ブルーノ・タウト
マックス・タウト
フランク・ティール
東郷青児
土浦亀城
津田青楓
妻木頼黄
ウンボ(オットー・ウンベール)
ヴォルフ・フォステル
和達知男
渡辺 譲
ヴィリアム・ヴァウアー
ユップ・ヴィエルツ
エメット・ウィリアムス
山田 守
山口(岡村)文象(蚊象)
山下菊二
山脇 巖
柳瀬正夢
横尾忠則
萬 鐡五郎
揚州周延
イヴァ
※姓のアルファベット順
東京−ベルリン展ポスター 国際広告賞で金賞を受賞!
 森美術館で開催した「東京-ベルリン/ベルリン-東京展」(2006年1月28日〜5月7日)のポスターが、ニューヨークで開催された国際広告賞「The One Show」の「One Show Design」部門において栄誉ある最高賞Gold Pencil(金賞)を受賞しました。
森美術館で開催した「東京-ベルリン/ベルリン-東京展」(2006年1月28日〜5月7日)のポスターが、ニューヨークで開催された国際広告賞「The One Show」の「One Show Design」部門において栄誉ある最高賞Gold Pencil(金賞)を受賞しました。
2006年度 One Show Designには世界30ヵ国から1800を超える作品の応募があり、61作品が「Pencil」を受賞。「Pencil」はファイナリストの中から特に優秀な作品に贈られる金・銀・銅賞で、その中から日本からの応募では唯一、森美術館の作品が金賞を受賞しました。
本展のポスターは、グッド・デザイン・カンパニー水野学氏のアートディレクションによるデザインです。
受賞作がThe One Showのウェブサイトにて紹介されています。
http://www.oneclub.org/oneshow/osd_awards.php?id=969
[The One Showとは]
「The One Show」は「カンヌ国際広告賞」「Clio Awards」と並ぶ「三大広告賞」のひとつとして知られています。毎年アメリカで開催されている同賞は、毎回トップクラスのクリエイティブ・ディレクターが審査員に名を連ね、世界各地のクリエイターにとって最も憧れる賞として知られています。

|
 |
| MAM SCREENは森美術館で開催中の展覧会に関連するアート映像を、月替わりで上映します。上映場所はメトロハットの屋外500インチスクリーンやウェストウォークのPDPモニターなど六本木ヒルズ内各所。詳細はこちら。 |
 |
| 「東京−ベルリン / ベルリン−東京展」に参加のベルリン在住アーティストを2006年4月まで特集します。 |
 |
1月
マルティン・リープシャー
《相乗り》
2004 |
 |
2月
アニカ・エリクソン
《公共の場での人々》
2000-2006
※メトロハット屋外500インチスクリーンにて毎日17:00から上映 |
 |
3月
キャンディス・ブレイツ&アレクサンダー・ファール
《スリラー》
2005
Courtesy: Bifrons Foundation
|
 |
4月
ニナ・フィッシャー&マロアン・エル・ザニ
《ベルリン(日の出) - 未来について10秒考える》
2000
Courtesy: Galerie EIGEN + ART Leipzig / Berlin and the artists
|
 |
|
|
 |


エルンスト・ルートヴィヒ・キルヒナー《ポツダム広場、ベルリン》 1914
油彩、カンヴァス 200×150cm
所蔵:ベルリン国立博物館群 ベルリン国立美術館
(c) (for works by E.L.Kirchner) by Ingeborg & Dr. Wolfgang Henze-Ketterer, Wichtrach / Bern
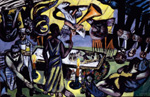
マックス・ベックマン《死》
1938 油彩、カンヴァス
121×176.5cm
所蔵:ベルリン国立博物館群 ベルリン国立美術館
Photo: Jörg P. Anders, Berlin / Jahn: 2001

ダヴィト・ブルリューク
《家族の肖像》
1921 油彩、カンヴァス
94.2×136.4cm
所蔵:兵庫県立美術館

マルティン・リープシャー
《フィルハーモニー 1》
2005 125cm×740cm
ラムダプリント
(クラウディア&クルト・フォン・シュトルフ コレクション)
Courtesy: Wohnmaschine, Berlin

岡本太郎《重工業》
1949 油彩、カンヴァス
206.3×266.7cm
所蔵:川崎市岡本太郎美術館

佐伯春虹《茶苑》
1936 紙本着色 264×197cm
個人蔵、アメリカ

ボリス・ミハイロフ《路上にて》 2001/03 150×100cm
タイプCプリント
Courtesy: Galerie Barbara Weiss, Berlin
Photo:Jeus Ziehe, Berlin
|
 森美術館で開催した「東京-ベルリン/ベルリン-東京展」(2006年1月28日〜5月7日)のポスターが、ニューヨークで開催された国際広告賞「
森美術館で開催した「東京-ベルリン/ベルリン-東京展」(2006年1月28日〜5月7日)のポスターが、ニューヨークで開催された国際広告賞「