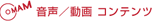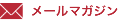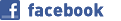前回「ネイチャー•センス展」に出展する吉岡徳仁、篠田太郎、栗林 隆といった3作家のテーマへのアプローチ、新作に触れながら、展覧会のみどころについて話したキューレーターの片岡真実に、今展に関わり新しく見えてきた日本の自然観とアートとの関係を聞いてみました。

--3作家のインスタレーション作品を通し、見えてくる自然観とはどのようなものでしょうか?
片岡:東京の都市空間も、自然の一部と捉える篠田さんの作品には、日常生活の営みも自然のサイクルの一断片でことを示唆しています。これまで話して来たように、日本の自然観を何らかの対象を持ったものではなく、対象の間をつなぐ何らかの超自然的なエネルギーやバイブレーションと関連させて考えると、現代の都市を生きる私たちの日常もその自然観の一部であることがはっきりします。このような自然あるいは超自然を知覚する潜在的な力(ネイチャー・センス)は、空間に神々や霊性(アニマ)を感じられる独自の宗教観、教義や組織という意味での宗教から離れた文化的な遺伝子となって脈々と受け継がれ、現代の美術やデザインに活かされていることを体感していただけると思います。
--西欧の作家がコンセプトから出発するのに対し、日本の作家は感覚的な自然観、宇宙との一体感を拠り所にしている。日本人はもっと五感を頼りにしてきたのかもしれませんね。
片岡:皮膚感覚など五感はすごく大切で、それは湿度の高い日本の気候とも関連していると思いますが、理性や知性として認識する以前の知覚段階で自然を感知できる。「もののけ姫」にコダマというキャラクターが出てきますが、実際、伊勢神宮とか森の中を歩くと、スピリチュアルなものの気配を感じる。人間、動物、植物だけでなく、命をもたない物にも魂が宿るというアニミズム的感覚は、仏教思想も吸収し、現代の私たちの中にも少なからず残っていると思います。

栗林 隆 《ゼーフント・ヒロシマ(アザラシ・ヒロシマ)》 2004
ネオプレン、ミクスト・メディア 1462×1411×680cm
展示風景:「ミュージアム・アドベンチャーの活動から」広島市現代美術館、2004
--アメリカインディアンなど先住民の例を見ても、日本に限らず、近代化が起こる以前の世界では、アニミズム的世界観が当たり前だったわけですね。
片岡:1960年代、それまで非合理的であるとされていた未開の文化や神話的思考に注目したレヴィ=ストロース(フランスの社会人類学者)しかり、元森美術館の館長デヴィット・エリオットがキュレーションした開催中のシドニービエンナーレでも、北アメリカやオーストラリアの先住民によるアートが多く見られて興味深く見ました。つまり、現在でもモダニズム的価値観から解放されれば、そこで置き去りにされてきた興味深い表現の再評価が世界各地で可能なのではないかと感じています。
--かつて工業化、近代化が極端に進んだ時、知識人やヒッピーがスピリチュアリズムを信奉したりしました。そういう揺り戻しが、今度はより一般の普遍的レベルで起こっているのでしょうか?
片岡:リーマンショックによる資本主義や新自由主義の象徴的破綻によって、89年の社会主義崩壊に続き、西欧中心の近代的思考が揺らいでいることは誰の目にも明らかになった。モダニズムの中で劣性に見られていた宗教的、呪術的、アニミズム的価値観が確実に再考されているように感じます。そんな今、改めて岡本太郎のようなアーティストを見直してみるととてもおもしろいと思います。

インタビュワー玉重氏(左)に本展の説明する片岡
--もう少し具体的に教えていただけますか?
片岡:岡本は、1930年代のパリ滞在中、フランスの文化人類学者マルセル・モースからも学び、バタイユらとも交友がありました。帰国後、縄文、アイヌ、沖縄などの文化から、日本の呪術的なものにある美や力を再発見していった。最先端の前衛芸術を担っているようでいて、実際には1950年代に日本文化のオリジンを考えていた人で、超自然的、四次元的な考察の必要性を説いています。
また今展のため自然観を考えている中で、もの派も別の新鮮な視点で見えてきました。
--もの派は石、木、紙、綿、鉄板、パラフィンといった〈もの〉を単体や組み合わせて作品とした、世界的にも知られた日本の現代美術の動向(1960年代末から70年代半ば)ですね。
片岡:もの派を理論づけたアーティストの李禹煥は、例えば自然石と鉄板を併置して、対象物同士の共鳴を太鼓の響きに譬えながら、その間のバイブレーションを知覚することを説いています。関根伸夫も『もの派--再考』展のカタログの中で、「昔ながらの東アジアの考え方、すなわち樹木や岩石は生きている、魂がある、存在しているとするアニミズム的な考え方に立ち戻った地帯だったといえるかもしれない」と回想しています。
--もの派が原初的な世界と繋がっていると知ると新しく感じられますね。日本古来の自然観が現代の私たちの身の回りに、それこそアニミズム的に偏在しているということでしょうか?
片岡:もの派は、物についての芸術ではなく、物と物の間に存在するエネルギーについての芸術と考えると、それはこれまで見て来た日本の自然観とまさに重なり合います。
私たちの日常の中にも、例えば祭祀や伝統行事など慣習化されたものがありますが、そこから超自然的、四次元的な感覚を紐解き、自然(じねん)の自然観に立ち戻ることで、日本の文化的本質が見えてくる気がします。
--ネイチャー•センスを喚起して、アートや日常、日本を見渡すと、新しい日本の像が立ち現われてくるようですね。
片岡:今展の背景のテーマ「日本を再定義する」ことは、政治的境界線としてのナショナリズム的日本でなく、文化的なアイデンティティーや遺伝子を考えることだと思っています。そして、そこから生み出される新たな創造性を、整理、分析して次世代に継承することの必要性を感じています。自分の立ち位置やオリジンを見直し、自らを知ることで、現在見えている世界中の異なる文化のアイデンティティーへのリスペクトや、これからの未来に求められる新しい価値観も見えてくるような気がしています。
(2010年6月1日、森美術館にて取材)
(聞き手:玉重佐知子)
【玉重佐知子プロフィール】
文化ジャーナリスト。早稲田大学卒。1988年渡英、ロンドンで西洋美術史、映画文化人類学を学んだ後、ロンドンを拠点にNHKやBBCなどのドキュメンタリー番組制作に関わる一方、美術、建築、デザインについて、アエラ、日経アーキテクチャー、BT(美術手帖)、Blue Print他に執筆。英国や日本の文化政策や文化を起爆剤にした地域振興戦略を追っている。書籍「Creative City アート戦略EU•日本のクリエイティブシティー」(国際交流基金/鹿島出版会)の一部執筆。
<関連リンク>
・連載インタビュー:ネイチャー・センス展を目前に(全4回)
第1回 日本の自然観を再考し、日本固有の文化を紐解く
第2回 「自然(しぜん)から「自然(じねん)」へ
第3回 「作家が紡ぎ出す、抽象化された自然のインスタレーション
第4回 「ネイチャー•センス」喚起!見えてくる日本のカタチ
・「ネイチャー・センス展: 吉岡徳仁、篠田太郎、栗林 隆
日本の自然知覚力を考える3人のインスタレーション日本の自然知覚力を再考する」
会期:2010年7月24日(土)~11月7日(日)
・