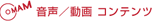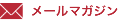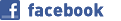世界で活躍するアーティスト、キュレーターなどをゲストに、最新のトピックスについて議論をする森美術館のシリーズ企画「アージェント・トーク」。昨年行なわれた「アージェント・トーク014:レアンドロ・エルリッヒ――視覚のトリックで現実を問い直す」では、金沢21世紀美術館の《スイミング・プール》で国内でも広く知られるようになった、レアンドロ・エルリッヒが登場。作品の紹介のほか、現実・世界認識のあり方、また日本的な感性、創造力、技術力の可能性について語りました。

レアンドロ・エルリッヒ
「毎日起こること、繰り返されること――当たり前で日常的で、明らかで共通していて、普通というよりは基礎的で、常に背景にある雑音、あるいは習慣のようなもの――に注意を払い、疑問を持ち、描写するにはどうすればよいのか?
我々はそれにあまりにも慣れていて、疑問を持ったりしないし、それは我々に疑問を提起したり、問題になることはない。それが、習慣的なものに問いかけることの難しさだ。」 (ジョルジュ・ペレック 『L'infra-ordinaire/基礎的なもの』より)(筆者拙訳)
冒頭でレアンドロ・エルリッヒは、上記のフランスの小説家ジョルジュ・ペレックの文章を引用してみせた。
視覚や聴覚に訴えるトリックを用いたエルリッヒの建築的な空間インスタレーションは、私たちの常識の隙間に入り込むことで成立している。日常的で、習慣的で、当然だと思われている事象に疑問を投げかけること、それが彼の芸術表現の根幹をなすといえる。
例えば、金沢21世紀美術館の《スイミング・プール》(図1)では、透明の樹脂が水面の見立てになっており、実際にプールの中に入っている人を外から観客が眺めることができる。新潟の越後妻有トリエンナーレ(2006)で展示された《妻有の家》(図2)では、床上の実物大の家の写真の上で観客が様々なポーズを取ると、斜めに設置された巨大な鏡に、垂直な家の壁の上で軽々と遊ぶ観客たちが映る。これはパリのアートセンター104でも行っており、いずれも大変な人気を博したそうだ。

図1 《スイミング・プール》
© Leandro ERLICH

図2 《妻有の家》
© Leandro ERLICH
初期の作品では、存在しないはずの空間をあるように見せるものが多い。例えば、シンプルなエレベーター状のオブジェの中に入ると、永遠に続くエレベーター・シャフト(昇降路)が見えたり、インターフォンの付いた奥行きの無いドアの覗き穴を覗くと、とても長い廊下が見えたりする。(図3)

図3 会場風景
他にもルイス・キャロルの『鏡の国のアリス』を想起させるインスタレーションとしては、全く同じ内装の部屋が左右対称に設置されることで間を繋ぐ開口部が鏡のように見える部屋(図4)や、3つの全く同じ部屋のセットに鏡の効果を加えることで、3人の太極拳を行う別人が、四方に映り込む同一人物であるかに見える部屋(図5)などがある。

図4 会場風景

図5 《El Ballet Studio》
3rd. Shanghai Biennial, China.
Performance Installation
© Leandro ERLICH
最近では視覚のみならず、聴覚に訴えることで、見えないものを可視化するようなインスタレーションも発表している。例えば、ウクライナでかつての炭鉱をアートセンターにした場所では、石炭の運搬に使っていた敷地内を走る高架状のトロッコの線路に100個ほどのスピーカーが一定間隔で装着され、そこからトロッコ列車の走る音が順番に流れる。するとまるで見えない列車が動き回り、その場所が炭鉱として機能していた時代にタイムスリップしたような感覚を観客に与える。(図6)


図6 下の写真の赤丸がスピーカーの位置
© Leandro ERLICH
エルリッヒは、こうした作品群は、観客が作品に対して相互関与(インタラクション)することで初めて成立すると語る。作品制作の際には作品が置かれる場のコンテクストと物語性を熟考し、人々がどのように反応するか、あるいは作品が人々に対してどのように作用するかを想像しながら作るそうだ。だからこそ、彼の作品は注意を引き、誰もが楽しめるものになるのだろう。建築家ばかりの家族の中で、一人、アーティストになることを選んだ理由も、空間の物理的・実質的な役割より物語性に興味があったからという事実からも、この姿勢は伺える。
感覚の隙間に入り込むトリックを用いた作品群は、観客に自らの感覚を行使しつつも、その感覚を疑うような作品鑑賞を課す。すなわち、現実とは個々人の捉え方、感じ方によることを気付かせ、さらにその感覚に疑問を呈することで全く違った現実存在の可能性を開示するのだ。
作品における鏡の多用について、「イタロ・カルヴィーノの『見えない都市』に出てくる湖畔の村――そこでは、村で起こるすべての事象が湖の水面に映し出されるため、人々は常に自分の行うことがどのように見えるか意識的であるのだが――における水面のように、現代都市において人々の行動を潜在的にコントロールするメディアとの類似性を提示しているのか?」と筆者が質問すると、「もちろん、そういったこともあるけれど、鏡には様々な哲学的な思考を提起する側面があり、例えばメディア以外にもパラレル・ワールドとか、もう一つの存在といったものを想起させることができるよね」と視野を広げてみせた。
日本についての印象としては、マナーから技術力に渡ってすべてが正確であること、また同時に繊細な感性を持ち、新しいアイデアや技術に興味を持って開かれており、新たに学んだものでも最終的には日本らしく洗練された、より素晴らしいものに変えることができることに感動したそうだ。デザイン、建築、音楽、表現、料理などを見ても日本は創造性に満ちており、例えば生魚を切って米(しゃり)の上に載せだけのシンプルな料理方法の寿司も、日本でなければ思いつかなかったのではと語った。しかしながら同時に日本社会はとても規則的で、縦社会で、固定観念に囚われているようにも思え、大変複雑な社会なのだと感じたという。

図7 会場の観客の様子
最後に「創造性を育むのに必要なことは?」という質問には「10人居たら、10人それぞれの意見、アイデアを同等に扱い、シェアする場所が必要だと思う」と語った。何かを頂点としたヒエラルキーに縛られた思考方法ではなく、このような今ある秩序を無化する多角的でネットワーク的な思考方法は、アートのみならず、今後の日本、世界においてますます重要になるのであろう。こうした思考方法は、当然とされる常識や権威的な前提に対し疑問を投じる行為、すなわちエルリッヒの作品手法自体にも、意外に近いのかもしれない。
文:椿 玲子(森美術館学芸部 アソシエイト・キュレーター)
レアンドロ・エルリッヒ(アーティスト)
1973年ブエノスアイレス(アルゼンチン)生まれ、現在ブエノスアイレス在住。2001年の「第49回ヴェネチア・ビエンナーレ」に出展した《プール》で国際的に知られるようになり、以降「イスタンブール・ビエンナーレ」(2001年)、「上海ビエンナーレ」、「釜山ビエンナーレ」(2002年)、「サンパウロ・ビエンナーレ」(2004年)、「シンガポール・ビエンナーレ」、「リバプール・ビエンナーレ」(2008年)など数々のビエンナーレに出展。近年の個展にソンウン・アート・スペース(ソウル、2012年)、国立ソフィア王妃芸術センター(マドリッド、2009年)、MoMA/P.S.1コンテンポラリー・アート・センター(ニューヨーク、2008年)など。
ホームページ(英語) http://www.leandroerlich.com.ar/
<関連リンク>
・アージェント・トーク008理想の未来像を描くことは簡単ではない 映像プログラム「スター・シティ」を上映
・アージェント・トーク009
ニナ・フィッシャー&マロアン・エル・ザニの映像作品に見る「歴史への視点」
・アージェント・トーク010
アート顧客拡大に向けたデジタル・メディアの効用法‐英国テートの例
・アージェント・トーク011
アジアの歴史的な美術や文化を現代に繋げる。サンフランシスコ、アジア美術館の進む道 ・アージェント・トーク013
世界最大の現代アートの祭典DOCUMENTA 13速報 存在感を出していたのは身体的な感覚に訴えかける作品